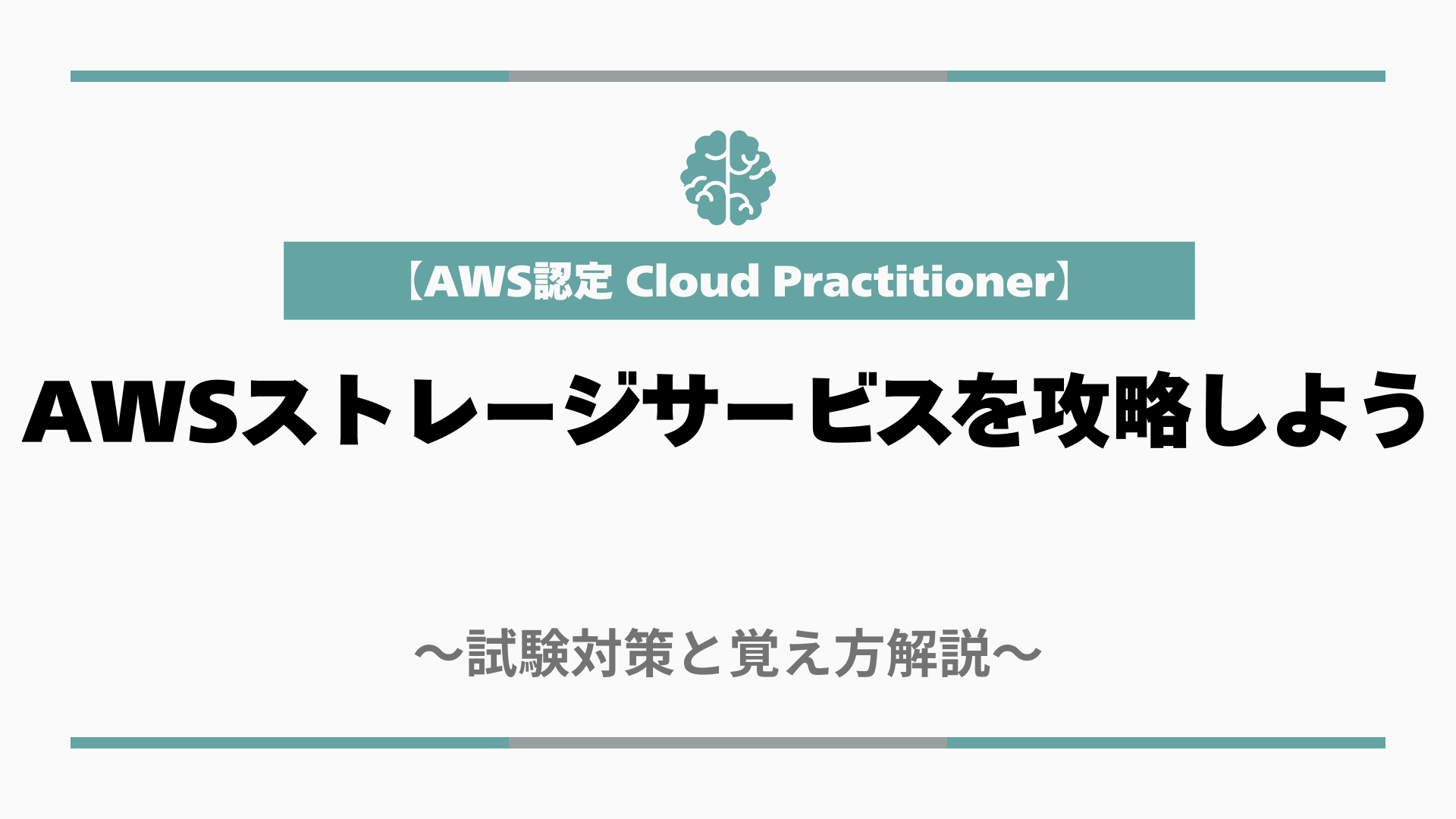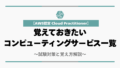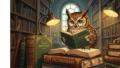はじめに
AWS(Amazon Web Services)には、データを保存するための多種多様なストレージサービスが用意されています。しかし、「それぞれの違いはなんだろう?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?特に資格試験の勉強をしていると、その数の多さに圧倒されてしまうかもしれません。
AWSのストレージサービスは確かに数が多いですが、Cloud Practitonerの試験対策としては、今回紹介する代表的なサービスをしっかり理解しておけば十分です!
この記事を読めば、「どんな保存の仕組みで、どんな用途に向いているのか」を明確に区別できるようになるはずです!
試験対策として効率よく学習できるよう、AWSの主要ストレージサービスをわかりやすい例えとポイントで解説していきます!
ストレージサービスの種類(分類で理解する)
AWSのストレージサービスはその特性によって大きく3つのカテゴリに分類できます。この分類を覚えておくだけでも試験では選択肢の絞り込みができます!
それぞれどのような特徴を持ったストレージなのか順番に解説していきます!
1. オブジェクトストレージ
- 代表例:Amazon S3、Amazon Glacier
- イメージ:巨大な「倉庫」にファイルを保管して、ラベルをつけて管理する
- 特徴:
- 無限に近い容量、非常に高い耐久性を持つ
- URLからアクセス可能(試験では「インターネットを通してアクセス可能」というワードが頻出です)、バックアップや配信に向いている
- Glacierは低コストだが取り出しに時間がかかる「冷凍倉庫」のようなもの
- 用途:静的サイト、画像・動画の保存、バックアップ、ログ保管、長期アーカイブなど
2. ファイルストレージ
- 代表例:Amazon EFS、Amazon FSx
- イメージ:みんなで共有する「フォルダ」
- 特徴:
- 複数サーバーから同時アクセス可能
- フォルダ構造で管理(階層的ディレクトリ)
- EFS:Linux向け、スケーラブル(拡張性が高いという意味)でフルマネージド(AWSが全て管理してくれるという意味)
- FSx:Windowsファイルサーバーや高性能Lustreファイルシステムなどをフルマネージドで提供
- 用途:社内共有フォルダ、Windows環境のファイルサーバーなど
3. ブロックストレージ
- 代表例:Amazon EBS、インスタンスストア
- イメージ:サーバーに直結する「ハードディスク」
- 特徴:
- OSやDBのように読み書き頻度が高いデータに最適
- EBS:永続的、EC2とセットで利用。停止・再起動してもデータ保持
- インスタンスストア:EC2の物理サーバーに直結した一時的なディスク。停止するとデータは消える
- 用途:
- EBS:システムディスク、データベースの保存
- インスタンスストア:キャッシュ、一時データ、処理用の一時領域
サービスごとの解説(詳細を理解する)
それでは、それぞれのサービスについて、具体的な特徴と分かりやすい例えを交えて解説していきましょう。
Amazon S3:インターネット上の「倉庫」
Amazon S3(Simple Storage Service)は、インターネット上に無数の荷物を収納できる巨大な「倉庫」のようなものです。写真、動画、ドキュメント、Webサイトのコンテンツなど、どんな種類のデータでも無制限に保存できます。
- 特徴:
- 高耐久性: データは複数の設備に自動で分散保存されるため、非常に高い耐久性を持っています。
- 高い可用性: いつでもどこからでもインターネットを経由してURLからアクセス可能です。
- スケーラブル: 保存容量に制限がなく、使った分だけ料金が発生する従量課金制なので、コスト効率も抜群です。
Amazon EBS:EC2専用の「HDD」
Amazon EBS(Elastic Block Store)は、EC2インスタンス(仮想サーバー)に接続して使う、専用の「HDD(ハードディスクドライブ)」のようなイメージで考えてください!主にOSやアプリケーションのインストール先として利用されます。
- 特徴:
- EC2とセット: 必ずEC2インスタンスと組み合わせて利用します。
- 永続的: EC2インスタンスを停止してもデータは残ります。ただし、EC2インスタンスを削除するとEBSボリュームも削除される設定の場合が多いので注意が必要です。
- 高速アクセス: ブロックレベルでのアクセスが可能で、データベースなどの高速I/O(インプット/アウトプットのこと)が求められる用途に適しています。
Amazon EFS:みんなで同時にアクセスできる「共有フォルダ」
Amazon EFS(Elastic File System)は、会社などで使う「共有フォルダ」のようなイメージです。複数のEC2インスタンスから同時にアクセスし、同じファイルを読み書きすることができます。
- 特徴:
- 複数アクセス: 複数のEC2インスタンス(主にLinux OS)から同時にアクセスし、データを共有できます。
- 自動スケーリング: 容量は必要に応じて自動的に拡張・縮小します。
- ファイルレベル: ファイルシステムとして機能するため、既存のアプリケーションとの連携も容易です。
Amazon Glacier:長期保存用の「冷凍倉庫」
Amazon Glacierは、その名の通り(Glacierは日本語で氷河という意味)、「冷凍倉庫」のように非常に安価でデータを長期保存できるサービスです。すぐに取り出す必要のない、法律で保存が義務付けられているデータや、バックアップデータなどに最適です。
- 特徴:
- 低コスト: 非常に安価にデータを保存できます。
- 取り出しに時間: データを取り出すには数分から数時間かかる場合があります。即時アクセスが必要なデータには向きません。
- 大容量アーカイブ: 大量のデータを低コストでアーカイブするのに特化しています。
試験対策のポイント
AWSストレージサービスは、試験でも頻出のテーマです。以下のポイントを押さえて効率的に学習しましょう。
- 名前と用途をセットで覚える: 「Amazon S3 = インターネット上の倉庫」「Amazon EBS = EC2専用のHDD」「Amazon EFS = みんなで使える共有フォルダ」といったように、それぞれのサービスの名前と役割(用途)をセットで覚えましょう。
- 「即時アクセスが必要か」「コスト優先か」で区別する問題が出やすい: 問題文で「すぐにデータにアクセスできる必要があるか」「とにかくコストを抑えたいか」といった条件が示された場合、どのサービスを選ぶべきかを見極める練習をしましょう。例えば、即時アクセスが必要ならGlacierは不適切だとわかるようにしておきましょう!
- EBS/EFS/S3の違いを図で整理して覚えると効率的: これらの3つのサービスは特に混同しやすいため、「アタッチできるEC2の数」「アクセス方式(ブロック/ファイル/オブジェクト)」「永続性」などの観点から、図や表で比較しながら整理すると理解が深まると思います!
まとめ
AWSのストレージサービスは、一見複雑に見えますが、それぞれの「保存の仕方」と「使い道の違い」をしっかり押さえることが最も重要です。
今回ご紹介したサービスは、AWSのストレージの基本であり、多くの企業で実際に利用されています。つまり、試験対策としてこれらの知識を身につけることは、そのまま実務で役立つスキルとも言えます!
ぜひこの記事を参考に、AWSストレージサービスの理解を深め、試験合格、そして実務での活躍を目指してください!